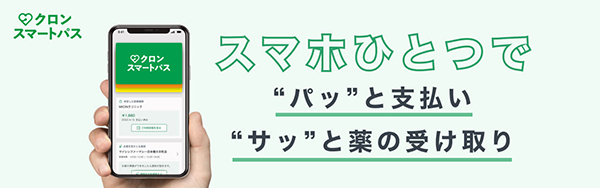- HOME>
- 当院の自費診療について
当院では高校生以上の方を対象に自費診療を行っており、18歳未満の方が受診される場合は保護者の同意が必要です。初めて自費診療を受ける方は、必ず医師の診察を受け、治療内容や頻度について相談のうえ、同意書にご署名いただくことがあります。また、20歳未満の方への一部自費診療は対応しておりませんのでご了承ください。
なお、インフルエンザワクチンなどの各種ワクチン接種や健康診断については、以下のURLより詳細をご確認ください。
ED(勃起不全)治療
ED 治療薬メニュー
※初診時はまずは1錠からのお試し処方となります。
ED治療薬の種類
| バイアグラ (シルデナフィル) |
シアリス (タダラフィル) |
|
|---|---|---|
| 特徴 | しっかり効果
ベーシック |
マイルドな効果 長期的に効く 最も副作用が少ない |
| 効果発現時間 | 約30分~1時間 | 約1時間 |
| 内服後の最大効果時間 | 約1時間後 | 約1-4時間後 |
| 持続時間 | 約5時間 | 約24-36時間 |
| 食事 (アルコール)の影響 |
受ける | ほぼ受けない |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※レビドラは当院での採用はなし
ED治療薬の費用(税込)(診察代を含む)
| 1錠 | 5錠 | 10錠 | |
|---|---|---|---|
| バイアグラ50mg | 1,800円 | 9,000円 | 18,000円 |
| シルデナフィル50mg (バイアグラジェネリック) |
1,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| シアリス20mg | 1,800円 | 9,000円 | 18,000円 |
| タタラフィル20mg (シアリスジェネリック) |
1,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
EDとは
EDは性行為に必要な勃起が得られない、あるいは継続できない勃起障害の状態です。不妊の原因となる場合も少なくありません。「勃たない」、「勃起しても硬さが不十分」、「性行為中に中折れする」などがEDの代表的な症状です。たまに性行為に支障をきたす程度の軽症から、時々・しばしば不具合を感じる中等度、そしていつも性行為ができない重症と個人差があります。
2002年に白井將文氏は40歳以上の日本人男性のうち5人に1人はEDであると報告しています。しかし病院で相談して治療を受けている方は多くありません。病気だとは思わずに年齢のせいにする、あるいは恥ずかしいからだと想定されています。
EDの種類と原因
EDは原因によって①動脈硬化や神経障害が関連する器質性ED、②精神状態やストレスが関わる心因性ED、③①と②が合わさる混合性ED、④ほかの理由で処方されている薬による薬剤性EDの4タイプに大別されます。
動脈硬化や神経障害は加齢ともに進行する場合が多いので、器質性EDや混合性EDは50歳以降で患者数が増加します。また動脈硬化と関連するメタボリックシンドローム、高血圧、糖尿病、脂質異常症の方や喫煙者がEDを患う場合も少なくありません。特に糖尿病は動脈硬化だけでなく神経障害とも関連します。
一方で心因性EDは30代や40代でも珍しくありません。ですからEDの原因は「年のせい」だとは限らないのです。
EDの診断方法|オンライン診療もご活用ください
EDの診断は問診で勃起障害の程度を評価して行います。問診内容は勃起を維持する自信の程度、性交刺激で挿入が可能な硬さの勃起を生じた頻度、性交中に勃起を維持できた頻度、勃起で支障を来たさずに満足に性交できた頻度などです。
EDはとてもデリケートな病気なので来院をためらう方が少なくありません。当院ではEDに対し条件を満たせばweb上で診療するオンライン診療を実施しています。現在は初回のみ来院していただく必要がありますが、将来は全てwebで完結する来院不要な診療システムを構築する予定です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
EDの治療方法
EDには治療薬がありますが、使用してはいけない場合(禁忌)があるために必ず医師による健康チェックが必要です。ED治療はほとんどが保険適応外の自由診療となるために費用は医療機関により異なりますが、ED治療薬は先発品で1錠につき1,500円~2,000円程度です。
医師に診てもらわずにインターネットや通販でED治療薬を購入する方がいますが、偽物や粗悪品が多いためにおすすめできません。そもそもED治療薬が禁忌の場合もありえます。
EDの原因となる糖尿病、高血圧、脂質異常症、メタボリックシンドロームなどがある場合はその治療も大切です。禁煙や肥満に対する減量など生活習慣の改善も欠かせません。
にんにく注射
にんにく注射メニュー
| ※現在、にんにく注射に使用するビタミン剤が出荷調整中となっております。 そのため、当院では にんにく注射の提供を一時的に中止 しております。 出荷調整が解消され次第、再開いたしますので、 患者様へはご不便をおかけいたしますが、 ご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
にんにく注射の種類と費用(税込)(診察代を含む)
| にんにく注射 | 1,650円 |
|---|---|
| にんにく“強化“注射(にんにく注射+マルチビタミン) | 1,800円 |
| にんにく“プレミアム”注射(にんにく注射+マルチビタミン+ビタミンC) | 2,200円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
にんにく注射(疲労回復注射)とは
にんにく注射は、ビタミンB1を主成分とした注射で、体内のエネルギー代謝を促進し、疲労回復をサポートする治療法です。ビタミンB群は、食事から摂取した栄養素をエネルギーに変換する働きを持ち、特にビタミンB1は疲労物質である乳酸の分解を助けるため、疲れやすい・だるい・元気が出ない・イライラするといった症状の改善が期待できます。
また、エネルギーの生成がスムーズになることで、免疫力の向上や肩こり・腰痛・筋肉痛の緩和にも役立つとされています。日常生活や食生活の見直しも重要ですが、慢性的な疲れを早く解消したい場合には、ビタミンB1に加え、ビタミンB6・B12などを含むビタミン注射が効果的です。にんにく注射でビタミンB群をしっかり補給し、疲れにくい健康的な体を目指しましょう。
にんにく注射の頻度
にんにく注射は即効性が期待できるため、疲労回復や体調改善を早く実感しやすいのが特徴ですが、その効果の持続期間は3日~1週間程度とされています。通常の接種頻度は1~2週間に1回が目安ですが、特に疲労が蓄積している方やストレスが多い方には、週に2~3回の接種がおすすめです。定期的に接種することで、より長く安定した効果を実感しやすくなります。体調やライフスタイルに合わせて、最適な頻度での接種を検討しましょう。
にんにく注射の効果
にんにく注射は、疲労回復や体調改善を目的としたビタミン注射で、エネルギー代謝を促進し、体の不調をサポートします。
こんな方におすすめ
- 仕事や育児、スポーツによる肉体疲労の回復
- 寝ても疲れが取れず、倦怠感が抜けない
- 二日酔いの回復
- 夏バテや季節の変わり目の体調不良
- 冷え性の改善
- 風邪を引きやすい、治りにくい
- 虚弱体質で体調を崩しやすい
- 緊張型頭痛、肩こり、腰痛の緩和
- 肌荒れやニキビの改善
にんにく注射に含まれるビタミンB群は、体内のエネルギー生成をサポートし、疲労物質の分解を促進するため、慢性的な疲れやストレスによる不調の改善が期待できます。疲れた体にビタミンのパワーを補給し、健康で元気な毎日を送りましょう!
水素ガス吸入療法
水素ガス吸入療法料金(税込)(診察代を含む)
| 水素ガス吸入(30分) | 2,500円 |
|---|
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※初回は、交換用チューブを1本1,000円(税込)でご購入いただきます。
水素ガス吸入は、継続することでより高い効果が期待できるため、通院が難しい方や日常的にケアを続けたい方には、ご自宅での使用をおすすめしています。クリニックでの施術とあわせてご利用いただくことで、より効率的に水素の力を取り入れることが可能です。興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
水素ガス吸入療法とは
水素ガス吸入療法とは、高濃度の水素ガスを吸入することで、体内の悪玉活性酸素を除去し、健康をサポートする新しい治療法です。近年、抗酸化作用や血流改善効果が期待されるとして注目されています。水素は体内に素早く吸収され、余分な活性酸素と結びついて水となり、尿や汗として排出されるため、副作用の心配が少ないとされています。
水素の単位には「PPM(parts per million)」が用いられます。たとえば、水素水では最大濃度が1.57PPMですが、水素ガス吸入では1万PPMという高濃度での吸入が可能です。この高濃度の水素を直接体内に取り込むことで、より効率よく抗酸化作用を発揮するとされています。
水素ガスの効果
1. 悪玉活性酸素の除去と抗酸化作用
水素は、体内の老化や病気の原因となる「悪玉活性酸素(ヒドロキシラジカル)」のみを選択的に除去する働きがあるといわれています。抗酸化力はビタミンCの176倍、ポリフェノールの221倍ともいわれ、身体の酸化ストレスを軽減し、細胞の健康維持に貢献すると考えられています。
2. 血流改善作用
水素ガスを吸入すると、血管が拡張し血流がスムーズになるといわれています。実際に、指先の末梢血管の血流を観察すると、吸入後に血液の流れが改善することが確認されることがあります。血流の改善によって、次のような効果が期待されます。
- 冷え性の改善:
血液循環が良くなることで、手足の冷えを緩和する可能性があります。 - 脳血流の向上:
脳の血流が滞ると、隠れ脳梗塞や集中力の低下を引き起こすことがありますが、水素の吸入で脳血流が良くなるといわれています。 - 美肌効果:
血流が良くなることで、肌のターンオーバーを促し、シミやくすみの改善につながる可能性があります。
3. 抗炎症作用
水素には炎症を抑える働きがあるといわれ、アレルギー症状やアトピー性皮膚炎、肌荒れ、花粉症による鼻のムズムズの軽減にも有効とされています。
4. リラックス効果と睡眠の質向上
水素ガス吸入は、自律神経の「副交感神経」を優位にするといわれています。これにより、以下のようなリラックス効果が期待されます。
- ストレスの軽減
- 疲労回復
- 質の高い睡眠
短時間の睡眠でも深い休息を得やすくなるため、慢性的な疲労を抱えている方や、睡眠不足を感じている方に適していると考えられます。
マイシグナル
miSignal®(マイシグナル))~尿で調べるがんリスク検診~
miSignal®(マイシグナル)は、尿に含まれるマイクロRNAを解析することで、「現在のがんリスク」と「将来のがんリスク」を部位別に評価するリスク評価型の検査です。
血液検査や生検などの侵襲的な検査と異なり、尿のみを採取する非侵襲的な検査方法で、身体への負担を抑えつつ、がんのリスクを客観的な数値で把握することができます。
最大9種類のがんを、1回の尿検査で評価可能
miSignal®(マイシグナル)では、1回の尿検査で最大9種類のがんについて個別にリスクを評価できます。
評価対象となるがんの種類
男性
肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、食道がん、膀胱がん、腎臓がん、前立腺がん(計8種類)
女性
卵巣がん、乳がん、肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、食道がん、膀胱がん、腎臓がん(計9種類)
2つの評価軸:「現在のがんリスク」と「将来のがんリスク」
現在のがんリスクとは
miSignal®(マイシグナル)では、AIを用いた尿中マイクロRNAの解析により、現在がんに罹患している可能性を評価します。
対象となるがん種は以下の通りです。
男性
肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、食道がん、膀胱がん、腎臓がん、前立腺がん(計8種類)
女性
卵巣がん、乳がん、肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、食道がん、膀胱がん、腎臓がん(計9種類)
※この評価は診断を確定するものではなく、あくまでもリスクの指標として提供されるものです。必要に応じて追加検査を行います。
将来のがんリスクとは
生活習慣や家族歴、環境要因などを考慮し、将来的にがんを発症する可能性を数値で評価します。がんリスクが高まる背景要因がある方にとって、予防的対策を検討する一助となります。
マイクロRNAとは?
マイクロRNA(microRNA)は、細胞間の情報伝達を担う小さなRNA分子の一種です。がん細胞を含む多くの病的状態において、特定のマイクロRNAの発現異常が確認されており、病気の発症や進行との関連が研究されています。
2000年代初頭から医学的な注目を集め、近年ではがん予防・診断支援の分野において活用が進められています。
既存のがん検査との違い
従来のがん検査は、腫瘍が一定以上の大きさになるまで発見が難しいという課題がありました。
miSignal®(マイシグナル)は、マイクロRNAのパターン変化を解析することで、腫瘍の大きさやステージに依存せず、比較的早い段階でのリスク評価が可能とされています。特に、ステージIやII相当の早期がんの兆候も検出対象に含まれる点が大きな特長です。
また、尿だけで評価ができるため、血液検査や内視鏡検査に抵抗がある方にもご利用いただきやすい検査です。
miSignal®(マイシグナル)の特長
1.早期リスク評価
マイクロRNAの変化を捉えることで、がんのリスクを早期に数値化します。
2.非侵襲的検査
採尿のみで行うため、身体への負担が少なく、痛みや出血を伴いません。
3.AIと遺伝子解析技術の活用
収集したデータはAIによって解析され、一定の精度でがんリスクを評価する仕組みとなっています。
4.パーソナライズド評価
遺伝的要因や生活背景をもとに、個人別のがんリスクとして評価される点が特徴です。
miSignal®(マイシグナル)をおすすめする方
- 家族にがんの既往歴がある方
- がんのリスクを感じている方
- 定期的ながんスクリーニングを受けたいが、侵襲的検査に抵抗がある方
- 健康診断・人間ドックの一環で、がんのリスク評価を追加したい方
- 将来的ながんの予防や早期発見に関心がある方
- 特定の生活習慣や遺伝的背景からがんリスクが高いと感じている方
miSignal®(マイシグナル)検査費用(税込)(診察代を含む)
| 尿で調べるがんリスク検診 (オールインワン) |
60,000円 |
|---|
男性
肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、食道がん、膀胱がん、腎臓がん、前立腺がん(計8種類)
女性
卵巣がん、乳がん、肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、食道がん、膀胱がん、腎臓がん(計9種類)
miSignal®(マイシグナル)検査の流れ
STEP1:採尿
当院にて採尿します。食事制限は不要で、簡単にご提出いただけます。
STEP2:解析
尿中のマイクロRNAをAIと遺伝子解析技術で評価し、現在および将来のがんリスクを数値化します。
STEP3:結果説明
約1か月後に結果をご説明します。リスクが高いと評価された場合は、必要に応じて追加検査や専門医療機関への紹介も行います。
miSignal®(マイシグナル)の結果報告書について
検査結果には以下の内容が含まれます。
- 評価されたがん種ごとのリスク数値
- 現在のリスクと将来リスクの両方の評価
- 必要に応じた今後の対応策(経過観察、再検査など)
※本検査結果は診断を目的としたものではありません。最終的な診断は、医師の判断および追加検査の結果によって行われます。
miSignal®(マイシグナル)は、がんの早期リスク評価を可能とする新しい選択肢です。「たぶん大丈夫」と思っていた健康状態に、客観的な根拠を持たせることができるこの検査は、今後の予防医療の一環として注目されています。
ご自身やご家族の健康に不安を感じている方、がんの早期発見を望まれる方は、ぜひ一度、当院にてご相談ください。
エピクロック
エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)とは?
体の真の年齢を測る次世代型バイオロジカルエイジ検査
「エピジェネティッククロック(epigeneticclock)」とは、私たちの身体がどれくらい老化しているか=生物学的年齢を科学的に“見える化”する検査方法です。これは、カレンダー年齢(暦年齢)ではなく、細胞やDNAレベルの変化をもとに算出される真の体内年齢を意味します。
当院で導入している「エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)」は、エピゲノム解析の最先端技術を用いた検査であり、日本人向けに最適化されたアルゴリズムを採用。検査によって得られる年齢データは、健康寿命や加齢性疾患リスクとも関連が深く、予防医療やアンチエイジング対策の土台となります。
エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)の仕組み:DNAメチル化でわかる“本当の年齢”
エピジェネティッククロックの基盤となるのは「DNAメチル化」です。DNAの特定の配列(CpGサイト)に化学的なメチル基が付加されることで、遺伝子の発現がオン・オフに切り替えられるスイッチのような働きをします。
このメチル化状態は、加齢だけでなく、食生活、運動、ストレス、睡眠などの生活習慣によって変化します。そのため、エピジェネティッククロックは、体の「経年劣化」をより正確に捉える手段として注目されているのです。
テロメアテストとの違い
| 比較項目 | エピジェネティッククロック | テロメアテスト |
|---|---|---|
| 測定対象 | DNAのメチル化パターン | 染色体の末端にあるテロメアの長さ |
| 精度・信頼性 | 高い(AIによる解析/臨床研究多数) | やや低め(個体差・変動が大きい) |
| 老化との相関性 | 強く、疾患リスクとの関係も確認されている | 間接的な指標にとどまる |
| 再測定の推奨頻度 | 半年〜1年ごと | 1〜2年ごと(あまり変化しない) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)の特長と提供する価値
特長1:日本人に最適化されたアルゴリズムを使用
欧米人向けに作られた従来モデルでは、日本人の体質・遺伝背景を十分に反映できませんでした。当院では、日本人200名以上のゲノムデータを基に開発された第2世代エピジェネティッククロック(PC-PhenoAge)を採用しています。
特長2:検査結果に基づくパーソナライズドアドバイス
・エイジギャップ:暦年齢と生物学的年齢の差(例:45歳の人の体内年齢が42歳など)
・老化スピード:1年間で身体が何歳分老化しているか
・生活習慣・血中タンパク指標:加齢に関連する20項目以上を評価
そのうえで、食事/運動/睡眠/サプリメントなど具体的な改善アクションプランを医師がご提案します。
特長3:短時間・簡単に実施できる検査
・所要時間
来院〜検査終了まで約30分〜1時間
・内容
問診+医師の説明+採血のみ
・結果通知
採血から6〜8週間後に郵送または来院で説明
このような方におすすめします
- 40代以降、老化や体力低下を自覚しはじめた方
- アンチエイジング治療に興味がある方
- エイジングケアの効果を数値で確認したい方
- 将来の健康リスクを先取りして対策を講じたい方
- 医療的・科学的な根拠に基づいて若さを維持したい方
エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)の費用(税込)(診察代を含む)
| エピクロック®テスト(1回) | 100,000円 |
|---|
※表は左右にスクロールして確認することができます。
エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)の検査の流れ
1.ご来院・受付
問診票の記入と受付対応(約10〜15分)
2.医師によるカウンセリング・ご説明
検査内容や結果の見方をご案内(約15分)
3.採血(検査自体)
必要な血液を採取(約5〜10分)
4.結果通知(6〜8週間後)
米国の解析機関よりレポートが届き次第、結果説明を行います。
臨床応用と研究分野での広がり
エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)は、今や美容やアンチエイジングだけでなく、以下のような臨床・研究領域でも幅広く応用されています。
- がん、心血管疾患、糖尿病など加齢関連疾患のリスク評価
- 健康寿命の推定
- 再生医療や細胞治療の品質管理
- 抗老化治療(HRT、NMN、栄養療法)の効果検証
- 薬剤・サプリメント開発におけるバイオマーカーとしての利用
“本当の年齢”を知ることが、健康の第一歩
エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)は、これからの予防医療・アンチエイジング・健康経営の中心的役割を担う技術です。「見た目の若さ」や「気持ちの若さ」だけでなく、DNAレベルでの若さを把握することで、科学的根拠に基づいた自己管理が可能となります。
半年〜1年に一度の検査によって、自分の身体と向き合う時間を持ちましょう。年齢に縛られない、自分らしい未来づくりの第一歩として、エピジェネティッククロック(エピクロック®テスト)の活用をご検討ください。
この記事の監修者情報

清水 導臣(しみず みちおみ)
清水医院(内科・外科・総合診療科) 院長
経歴
2006年 近畿大学医学部附属病院 初期研修医
2008年 市立岸和田市民病院 血液内科専攻医(研修)
2010年 関西医科大学附属枚方病院 救命救急センター助教
2011年 大阪府済生会野江病院 救急集中治療科医員
2017年 生長会ベルランド総合病院 急病救急科医長
2019年 京都市立病院 救急科医長
2021年 清水医院 院長
ご挨拶
京都府京都市右京区の内科・総合診療科の清水医院の院長の清水導臣です。
私は救急医として多くの患者さんを診てきた経験から、患者さんと身近に接し、信頼関係を築くことで、安心して治療や生き方を選択できる環境を提供したいと考えています。デリケートな内容も気軽に相談できる関係を大切にし、健康寿命の延伸や病気の予防につなげることを目指しています。そのため、対話を重視し、どのような不安や悩みもまずは気軽にご相談いただける医院を目指しています。